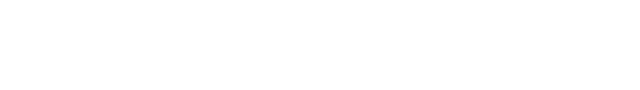乳がん
このページでは乳がんの症状・診断・治療についてご紹介しています。
はじめに
日本では年間9万人以上が乳がんに罹患し、14000人以上が亡くなっています(2019年がん統計)。
多くの癌は年齢とともに罹患率が上がりますが、乳癌は女性ホルモンが発生に関与していることから、40~50歳代という若い女性に多いという点がほかの癌と異なる点です。
乳癌の発生には他に遺伝や人種などが関係しており、未婚・未産・高齢出産・早い初経や遅い閉経・閉経後の肥満などがリスク因子と言われています。
ライフスタイルの変化により、日本でも乳癌が増えてきており、今後ますます増えていくだろうと予想されています。
部位別にみた悪性新生物の罹患順位(患者数)(2018年)
第1位
第2位
第3位
第4位
第5位
男性
前立腺
(92,021)
胃
(86,905)
大腸
(86,414)
肺
(82,046)
肝
(26,163)
女性
乳房
(93,858)
大腸
(65,840)
肺
(40,777)
胃
(39,103)
子宮
(28,542)
部位別にみた悪性新生物の死因順位(患者数)(2019年)
第1位
第2位
第3位
第4位
第5位
男性
肺
(53,338)
胃
(28,043)
大腸
(27,416)
膵
(18,124)
肝
(16,750)
女性
大腸
(24,004)
肺
(22,056)
膵
(18,232)
胃
(14,888)
乳房
(14,839)
女性の年齢階級別がん罹患率(2017年)
※緑色が乳癌罹患率を示す。
この図を見ると分かるとおり、40代~60代に罹患率のピークがありますが、70歳以上でも極端に少なくなるわけではありません。
お元気なうちは定期的に検診を受けられたほうがいいでしょう。
乳癌の進行はゆっくりであることが多く、また再発しても治療法が複数存在することから、ほかの癌と違って10年生存率で評価されます。
症状
腫瘍が5mm~1cmほどの大きさになると乳房の中にしこりを触れることがあります。
しこりは石のように硬く触れることもあれば、脂肪の塊のように柔らかく触れるものもあります。
良性の場合は月経周期によりサイズが変化することが多いですが、乳癌のしこりは月経周期による影響を受けません。
ほかに乳頭や乳房皮膚のひきつれ、発赤、びらん(すりきれのような赤み)、乳房痛、乳腺異常分泌などがみられることがあります。
早期ではまったく症状がないことの方が多いので、定期的に乳癌検診を受けることが大切です。
診断
あらゆる癌は発生してから一定の大きさになるまで発見することはできません。
一般的に乳癌検診の感度は90%ほど、特異度は95%ほどと言われています。
これは10%ほどの癌は見落とされるということを意味しています。
われわれ医師は当然極力見落としを少なくしようと最大限努めていますが、残念ながら現代医学では0%にできません。
そのため乳癌検診を受けられた方でも月に1回はセルフチェックをし、おかしいと思ったら(しこりや乳房のひきつれ)次の検診を待たずに受診してください。
視触診
まず乳房のひきつれや皮膚の異常がないか観察します。次にしこりがないか触診をします。
このとき脇のリンパ節が腫れてないかも確認する場合があります。
マンモグラフィ
乳腺の重なりを少なくするために2枚の板の間に乳房を挟んで薄く延ばして、レントゲンで乳房を撮影します(そのため痛いとおっしゃる方が多いです!)
早期乳癌の手がかりとなる石灰化という所見や、乳房の構造的な乱れを一見して捉えやすいという強みがあり、乳癌の標準的な検査ですが、若い女性では乳腺が発達しているため(高濃度乳房)、腫瘤の確認がしづらいというのが欠点です。
春日井市の検診では診察する医師のほか、別の医師が独自の判断で読影をしています(二次読影)。
超音波検査
乳房にゼリーを塗って乳房内を動画で詳しく調べる検査です。
マンモグラフィで捉え難い病変を、周囲の正常乳腺とは異質な構造として認識しやすく、リアルタイムの動画として様々な角度で観察できる特徴があり、マンモグラフィで腫瘤の観察が難しい若い女性にも適した検査です。また痛くないのも利点です。
それぞれの検査に利点・欠点があるため、2つの検査をうまく組み合わせることが大事と考えています。
自治体の検診助成は従来マンモグラフィのみが対象でした。平成27年に日本で40歳代女性の乳癌検診を対象にした研究でマンモグラフィに超音波を併用することでマンモグラフィ単独と比べ乳癌の発見率が1.5倍になったとの研究結果が発表されました。
これを契機にして、最近春日井市でも自治体検診の助成対象になりました。
当院の乳癌検診ではどちらか一方を選択することもできますし、両方を同じ日に受けることも可能です。
細胞診
超音波で観察しながら腫瘤の近くまで針を刺し、組織を注射器で吸引します。
吸引した液体を顕微鏡検査に提出し、癌細胞がいないかチェックします。出血が少ないのが利点ですが、偽陰性率が20~30%で認められます。
針生検
超音波で観察しながら腫瘤の近くまで太めの針を刺し、細長く組織を採取します。
採取した組織を顕微鏡検査に提出し、癌細胞がいないかチェックします。
出血の確率が若干高いのが難点ですが、細胞診に比べ偽陰性率が低いのが利点です。
組織検査により癌と診断されれば治療が可能な病院へ紹介することとなります。
当院は名古屋徳洲会総合病院、春日井市民病院、名古屋大学医学部附属病院と提携しており、紹介状をもって受診していただきます。
治療
早期癌の段階で見つかれば局所療法をまず考えます。
補助治療として全身療法を組み合わせることもあります。
一方、見つかった時に進行癌と診断されれば全身療法が治療の中心になります。
局所療法
(a) 乳房温存術
腫瘍の大きさ、広がりが限られている場合、腫瘍の周囲に1~2cmの正常乳腺組織をつけて切除します。
腫瘍径3cm未満で限局している場合に適応となり、手術症例の約半数が当てはまります。
診断時に乳房温存術の適応にならなくても、術前化学療法にて腫瘍が小さくなり、乳房温存術が可能になることもあります。
乳房温存術というとほとんど乳房が残るように聞こえますが、手術した側の乳房は反対側に比べ、小さくなったりいびつになったりします。
例えば2cmの腫瘍でも2cmずつ正常乳腺組織をつけて切除すると、直径6cmほど切除することになるからです。
乳房温存術を行う場合には残った乳房内に局所再発することを予防するために放射線療法を追加することが一般的です。
放射線療法をしないと約30%の方で再発するところが、放射線療法を追加すると約10%に低下することが知られています。
放射線照射により皮膚が硬くなることもあります。初めから乳房を全部切除して、後日形成外科で乳房再建術をするほうがきれいになることもあります。
とても悩ましいところではありますが、乳房温存術を希望される場合にはメリット、デメリットをよく理解して術式を決めることが大事です。
(b) 乳房切除術
乳頭・乳輪を含む皮膚の一部と、すべての乳腺、腋窩・鎖骨下リンパ節を切除します。
胸筋の一部を切除する場合もあります。
腫瘍径3cm以上、または癌が乳房内で広がっている場合に適応となります。
どちらの手術でも原則としてリンパ節生検やリンパ節郭清を施行します。
全身療法
内分泌療法
乳癌の多くは、女性ホルモンの一つであるエストロゲンにより増殖します。
内分泌療法はエストロゲンの分泌を抑えたり、エストロゲンの作用をブロックしたりします。全体の2/3の症例で効果があります。
吐き気や脱毛といった重い副作用が少ないという特徴があります。
化学療法
内分泌療法が効かなくなった症例や有効性が低いことが予想される症例に選択されたり、手術の前後に投与したりします。
飲み薬タイプと点滴タイプがあります。一般的に飲み薬タイプのほうが副作用が少なく、点滴タイプのほうが強力です。
点滴タイプの抗がん剤はいくつかの種類を組み合わせて投与することが多いです。
分子標的薬や免疫療法
腫瘍が特別な分子を発現している場合、それらの分子をブロックする薬剤が効果を示すことがあります。