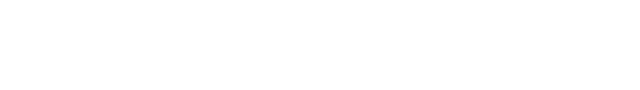生活習慣病
このページでは主な生活習慣病の種類についてご紹介しています。
生活習慣病とは食生活、運動習慣、喫煙、飲酒、睡眠等の生活習慣が、発症や進行に関与する疾患の総称です。
生活習慣病の中でも、高血圧、脂質異常症(高脂血症)、糖尿病、高尿酸血症は罹患人数が多い病気です。身近な病気ですが、初期には自覚症状がない場合が多く、放置しがちです。生活習慣病を長年放置すると、心臓病・脳卒中・腎臓病を発症する場合や、健康寿命が著しく低下し要介護生活になってしまう危険性もあります。
生活習慣病は、遺伝や社会環境など個人の責任ではない要因も関与していますが、ほとんどが長年の生活習慣の乱れが原因です。生活習慣病の予防としては、バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙、ストレス管理、良質な睡眠、定期的な健康チェックなどが有効です。
生活習慣を改めても数値の改善がみられない場合には薬物療法を始めます。
よく『薬を始めたら一生続ける必要がある』と思い込んでいる方がみえますが、決してそんなことはありません。
よい生活習慣を続けることで、徐々に薬を減らしていき、薬なしとなる方もしばしばいらっしゃいます。
詳しくは個別の紹介ページをご覧ください。